― 子ども・高齢者を守る“家庭防衛術” ―
- はじめに|誰もが狙われる時代の“家庭防衛術”
- 1. ネットに「個人情報」を絶対に書き込まない
- 2. 「知らない人」からのメッセージは開かず、返信しない
- 3. パスワードは「共有しない」「推測されにくく」「使い回さない」
- 4. 「無料」「当選」は99%詐欺と考える
- 5. SNS投稿の「写真」に潜む危険
- 6. LINEやメールで「お金」の話が出たらまず疑う
- 7. 「いいね」や「シェア」も責任を持って
- 8. フリーWi-Fiでは個人情報を入力しない
- 9. 子どもには「利用時間の制限」と「見守り」
- 10. 高齢者には「最新の詐欺パターン」を定期的に伝える
- まとめ|“家庭全体”で取り組むネット防衛の時代
- Q & A(よくある質問と回答)
はじめに|誰もが狙われる時代の“家庭防衛術”
LINEで突然届く「コンビニでiTunesカードを買ってほしい」といった“ギフト詐欺”、InstagramのDMに現れる“親切な第三者”、そして「孫からLINEが来たから…」と語る高齢者の詐欺被害。
これらはすべて、日常の中に忍び寄る“ネット犯罪”の一例です。
今や子どもも高齢者もインターネットと無縁ではいられない時代。情報弱者が最も狙われやすいこの現実に対し、家庭でできる「防衛術」が求められています。
この記事では、家族全員で共有すべきネットリテラシーの基本ルールを、実践しやすい形で10項目にまとめました。
1. ネットに「個人情報」を絶対に書き込まない
本名・住所・電話番号・勤務先・学校名などはもちろん、SNSに投稿した写真の「背景」にも注意が必要です。
表札、制服、通学路など、思わぬ形で“自宅”や“家族構成”が特定されてしまうケースがあります。
2. 「知らない人」からのメッセージは開かず、返信しない
詐欺師は、友人を装った「なりすまし」で接近してくることがあります。
「こんにちは」「助けて」などの一見自然な言葉には要注意。即ブロック、既読スルーでの対応が基本です。
3. パスワードは「共有しない」「推測されにくく」「使い回さない」
「1234」「abcd」「password」などは攻撃者にとって格好の的。
最低でも英数字混在+8文字以上、2段階認証の併用を推奨します。家族間でもパスワードは共有せず、それぞれの管理を。
4. 「無料」「当選」は99%詐欺と考える
「あなたが選ばれました」「今すぐ受け取りを」などのLINEメッセージ、SNS広告リンクには要警戒。
ギフトコードを送らせる詐欺が横行しており、家族間で「本物かどうか」確認し合う仕組みが重要です。
5. SNS投稿の「写真」に潜む危険
子どもの制服姿、自宅前での撮影、通学中の様子――これらが投稿されることで「居場所」が割れてしまう可能性があります。
投稿前の見直しを、家族ぐるみで習慣づけましょう。
6. LINEやメールで「お金」の話が出たらまず疑う
高齢者を狙う「孫からのLINE詐欺」や、恋愛感情を利用した「送金詐欺」も増加中。
誰であっても、金銭が絡むやり取りは“本人確認”が必須です。
7. 「いいね」や「シェア」も責任を持って
誤情報や煽り投稿を拡散しないように。「〇〇が危険」「拡散希望」などの投稿は、一度立ち止まって情報源を確認するクセを。
8. フリーWi-Fiでは個人情報を入力しない
駅・カフェなどのフリーWi-Fiでは、通信が盗聴されるリスクがあります。ログイン、カード決済、重要な入力操作は避けましょう。
VPNアプリの活用もおすすめです。
9. 子どもには「利用時間の制限」と「見守り」
深夜のスマホ使用や長時間視聴は、依存や詐欺被害に直結します。
フィルタリングツールの導入に加え、家族との“ルールづくり”が重要です。
10. 高齢者には「最新の詐欺パターン」を定期的に伝える
「LINEで孫からメッセージが来た」「携帯の支払いが未納と言われた」など、高齢者向けの詐欺は日々進化しています。
家族が定期的に事例を共有し、リテラシーを“共育”することが一番の防御です。
まとめ|“家庭全体”で取り組むネット防衛の時代
ネットは便利で楽しい反面、一歩間違えれば大きなリスクにつながります。
そしてその被害者になりやすいのが、「子ども」と「高齢者」です。
だからこそ、ネットリテラシーは“家族ぐるみで守る力”。
cyber-safety.jp では今後も、実用的でわかりやすいデジタル安全情報をお届けし、“家庭防衛”の実現を支援していきます。
Q & A(よくある質問と回答)
Q1. ネットリテラシーって具体的に何を指すの?
A. ネットリテラシーとは、インターネットを安全に、正しく使うための「情報の読み取り・判断・活用」の能力です。詐欺や情報漏えいから身を守る知識や行動が含まれます。
Q2. なぜ子どもや高齢者が狙われやすいのですか?
A. 子どもは経験不足で判断が甘く、高齢者は技術的な知識に乏しい場合が多いため、詐欺やフィッシング、なりすましのターゲットになりやすいからです。
Q3. SNS投稿で気をつけるべきことは?
A. 写真に写る制服や表札、通学経路などの“生活情報”で個人が特定される可能性があります。投稿前には必ず内容を確認し、プライバシー設定も見直しましょう。
Q4. フィルタリングアプリは本当に必要ですか?
A. はい。とくに未成年の端末には有効です。時間制限や閲覧可能なサイトを制御することで、不適切なコンテンツやネット依存から子どもを守れます。
Q5. 高齢の親にネットの危険性をどう伝えればいい?
A. 実際の詐欺事例をテレビや新聞で一緒に見ながら、「こういう被害があるから気をつけてね」と優しく、繰り返し伝えることが効果的です。


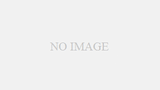

コメント